- 最近のできごと
- 2024年度米 売り切れのご案内
- 昔と今のお米づくりの違い
紙面でご覧になりたい方はコチラから。
最近のできごと
こんにちは、源四郎のお米生産者の高橋です。寒さが厳しい日々が続いていますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?ここ福山新田でも連日の寒波により、ついに積雪が4mを超える状況となりました。ここ数年はここまでの大雪になることは珍しく、久しぶりに家の周りの除雪や屋根の雪下ろしに追われる日々を過ごしています。
さて、積雪が4mを超えると一番の問題は「雪のやり場」です。すでに2階建ての屋根よりも雪の方が高くなり、屋根の雪を下ろしたくても下ろす場所がない状態になっています。こうなると人力ではどうにもならず、最終的にはパワーショベルなどの重機に頼らざるを得なくなります。昔の人達はこのような豪雪をどのように乗り越えていたのだろうかと考えると、改めてその知恵や体力の凄さに驚かされます。
また、これだけの雪が積もると春の農作業にも影響してきます。この分だと、今年の米作りは例年よりも少し遅れてのスタートとなりそう。またこちらのニュースレターでも追って状況をお伝えできればと思います。
今年も美味しいお米を育てられるよう、しっかり準備を進めていきますので、どうぞ楽しみにお待ちください!
2024年度米、売り切れのご案内
いつも源四郎のお米をご愛顧いただき、ありがとうございます!おかげさまで、2024年度に収穫したお米はすべて完売となりました。定期でご購入いただいている方、毎年リピートしてくださる方、新たにご購入いただいた方、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。しかしながら、お米をお求めいただいたにもかかわらずご用意できなかったお客様もいらっしゃったこと、大変申し訳なく思っております。ご不便をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。
2025年度産の新米予約は、夏頃から受付開始予定です。詳細は、改めてホームページやニュースレターでご案内いたします。引き続き、源四郎のお米を、どうぞよろしくお願いします。
お米の豆知識:昔と今のお米づくりの違い

今回は生活に役立つ知識という訳ではなく、お米の歴史に焦点を当ててお話しできればと思います。
お米作りの歴史は長く、日本では弥生時代から稲作が始まったとされています。昔と今では農業の技術が大きく進化し、作業の負担もずいぶん変わりました。昔はそれぞれの田んぼが、とても小さく、いろんなところに点在していましたが、今では機械化に伴い、田んぼは一箇所に集中し、作業しやすいように田んぼ一枚あたりの大きさもどんどん大きくなっています。今回は、昔と今のお米作りの違いについて「田植えと稲刈り」の違いについてご紹介します!
田植えの違い
昔(手植え)
昔は苗を1本1本手で植える「手植え」が一般的でした。農家総出で田んぼに入り、膝まで泥に浸かりながら苗を植える作業は、私自身体験しましたが、かなりの重労働。田植えの時期には、地域の人々が集まり、助け合いながら作業を行っていました。
今(田植え機)
今では田植え機を使い、大量の苗を一度に植えられるようになりました。田植え機はまっすぐ均等に植えることができるため、発育が揃いやすく収量の安定にもつながります。昔と比べて、作業時間が大幅に短縮されました。
収穫の違い
昔(鎌で手刈り・はさがけ)
昔は鎌を使って手作業で刈り取るのが主流でした。刈った稲は「はさがけ」と呼ばれる木の骨組みに掛け、自然乾燥させることで、じっくりと甘みを引き出していました。この乾燥方法は今でもやってらっしゃる農家さんもいます。
今(コンバイン)
現在はコンバインという機械を使い、稲刈りと脱穀を同時に行えるようになりました。昔は1日がかりだった作業が、今では数時間で終わるようになり、大幅に労力が削減されています。
まとめ
昔の農業は手作業が中心で、多くの人手と時間が必要でした。
しかし、今でも「はさがけ米」など、伝統的な手法にこだわる農家さんもいます。こうして時代とともに進化しながらも、変わらず美味しいお米を届けるための努力は今も昔も変わりません。
昔の農法と現代の農法の違いを意識しながら、お米を味わってみるのも、また楽しいかと思います。

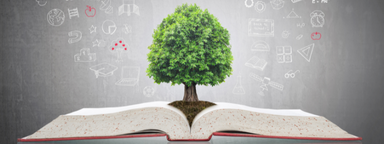





コメント