- 最近のできごと
- 今月の米づくり
- お米の豆知識「稲の成長」
紙面でご覧になりたい方はコチラ。
最近のできごと
こんにちは、源四郎のお米生産者の高橋です。連日厳しい暑さが続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?ここ福山新田でも、じっとしているだけでも汗が噴き出す日々です。皆様も熱中症にはご注意ください。
今年は梅雨らしい梅雨がほとんどなく、例年に比べて極端に雨の少ない日が続いています。ここ福山新田も、その影響を大きく受けています。山の上に位置するこの地域では、普段なら山間部に降る雨や湧き水が田んぼを潤す大切な水源となります。しかし、これほど長く雨が降らない状況が続くと、雪解け水などで豊かに流れ込むはずの水も心細くなり、田んぼ全体に十分な水を張るのが難しくなってきました。
さらに、日中は連日のように30度を超える真夏日が続き、容赦ない日差しが田んぼの水を奪っていきます。水の確保は米づくりにおいて最も重要なことの一つです。
今はちょうど稲が穂を作る大切な時期。田んぼの水管理は稲の健やかな成長に直結しています。水が不足すると、稲は大きなストレスを受け、成長が鈍ったり病気のリスクが高まったりします。
だからこそ、一枚一枚の田んぼの水位や土の状態を見守り、稲が安心して穂を実らせられるよう環境を整えていきたいと思います。
今月の米づくり
いつも「源四郎のお米」をご愛顧いただき、本当にありがとうございます。さて、今年の稲も今のところ稲は順調に育っており、いよいよ2025年度産・新米のご予約受付を8月1日(金)からスタートいたします。
昨年はおかげさまでたくさんのご注文をいただき、こちらで確保していた量が足りず、泣く泣くお断りしてしまったお客様もいらっしゃいました。今年はその反省を活かし、できるだけ多めにご用意できればと考えています。
ただ、出荷量との兼ね合いもあるため、あらかじめご予約いただけるととても助かります。昨年のように「もうお米がない…」とならないよう、ぜひお早めのご予約をお願いできれば嬉しいです。
お米の豆知識「稲の成長」

私たちが日々食べているお米が、どのようにして育っていくのか、その成長の過程をご存知でしょうか?今回は、田植え後の田んぼで進む稲の成長についてご紹介します。
分げつ期(ぶんげつき)
田植え後、稲はまず根元から新しい茎を次々と出し、本数を増やしていきます。これを「分げつ」と呼び、「源四郎のお米」の稲も、1株から15本から18本ほどにまで増やすが目安と言われています。この時期の適切な水管理が、稲の生育の基礎を築きます。
出穂期(しゅっすいき)
分げつが十分に終わると(通常は中干しによって分げつを止めます)、稲は次に実をつける準備に入ります。葉の根元に隠れていた穂が、ぐんぐんと伸びて葉の中から顔を出すのが「出穂」です。この時期の稲は、生命力に満ち溢れています。
開花期(かいかき)
出穂した穂には、ごく小さな花が咲きます。この花は数時間で咲き終わり、すぐに受粉します。この開花期の天候が、その年のお米の収穫量や品質に大きく影響すると言われています。
登熟期(とうじゅくき)
開花が終わると、いよいよ稲の最も重要な時期である「登熟期」に入ります。もみの中にデンプンが蓄えられ、実がどんどん太くなっていきます。この間、稲の色は青々とした緑から、徐々に黄金色へと変化し、秋の収穫に向けて準備を進めます。この時期の気候条件や水管理が、お米の甘みやツヤ、粘りを左右する重要な要素となります。
今年の「源四郎のお米」も、これらの段階を経て、皆様に自信を持ってお届けできる美味しいお米に育ってくれることと信じています。収穫まで残り2ヶ月ほど、気を抜かず、大切に育てていきたいと思います。

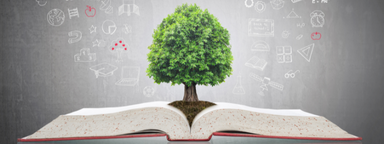





コメント